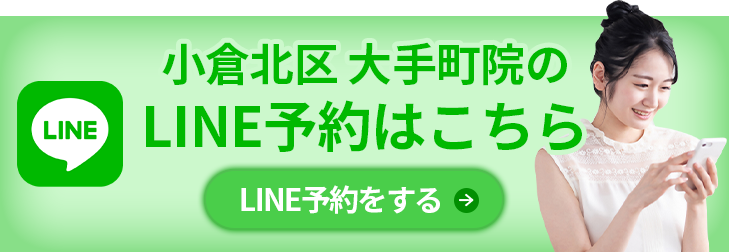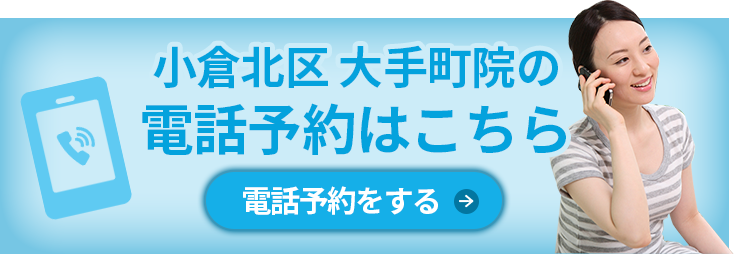ヒトはなぜ座るのか?section3
今日は「ヒトはなぜ座るのか?」シリーズ(section3)です。今回は【生活習慣】についてみていきます。人間はその昔、獲物を分け合い、みんなで一緒に食事をする習慣を身に着けます。その際、車座になって座り、目線を合わせることで「寛ぐ」という状態を覚えたのです。やがて人類は椅子という発明をします。日本には古墳時代から椅子は存在していましたが庶民一般に普及したのは戦後の高度経済成長期以降です。椅子の需要が伸びなかったのは畳や床の上に直接床に腰を下ろしていた「床座」の習慣が日本人の伝統的な生活でありました。現代人のライフスタイルが急激に変化する中で、2000年ごろから長時間座ることのデメリットが世界中で論じられるようになりました。section1で述べた「座る時間と総死亡率に関する研究」は、座り過ぎが健康リスクを高める仕組みは長時間の座位姿勢によって筋交感神経活動が高まり血管機能が低下、座り過ぎることで大腿部の筋活動が低下し血流を悪くし、代謝疾患や心血管障害のリスクを高めると報告しています。ある研究では1時間座り続けることで平均寿命が22分ほど短くなるというデータも報告されています。【まとめ】週末に運動していいるから自分は大丈夫などと考えている方もいるかもしれませんが、残念ながらそれでは座り過ぎによる悪影響は改善されません。もちろんジムに行って運動することは素晴らしいことですが、座っている仕事中などに少なくとも1時間に一回立ち上がって少し動くだけで健康リスクが減少することが最新研究で分かってきています。気づけば長く座っていしまっている方はこれからすこしでも立ち上がって体を動かすようにして座り過ぎを見直していきましょう。次回は「正しい座り方」についてです。お楽しみに!